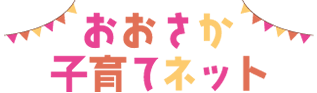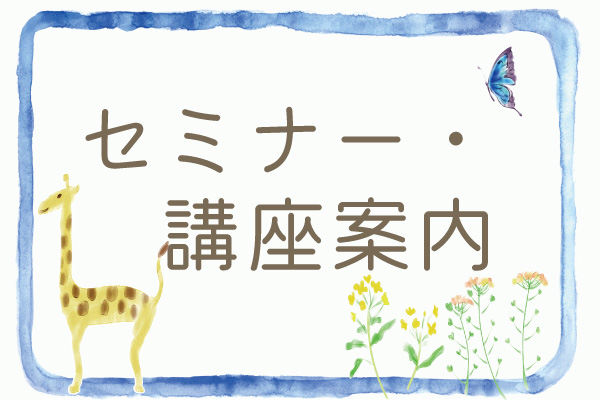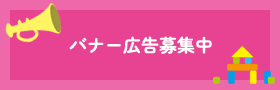子どもたちにすくすく育ってもらいたい・・・
男女がともに育児ができ、個性や能力を発揮できるように・・・
お知らせ
NEWS
クレオ大阪子育て館って
ABOUT US
「クレオ大阪子育て館」は、多様化する子育てニーズやライフスタイルにお応えします。
相談
子育て相談 TEL:06-6354-4152(電話相談・面接相談予約)女性の悩み相談 TEL:06-6770-7730(面接相談予約・クレオ大阪女性総合相談センター)
男性の悩み相談
講座・イベントなどの開催
子育てを支援する講座男女共同参画に関する講座
イベント事業
地域の子育て活動の支援
子育て支援機関や団体・サークルと連携した取組み図書・遊具貸出サービス「いろいろレンタ」の実施
保育室開放カレンダー
CALENDAR
- 保護者と子どもが自由に利用できます。
- おもちゃや絵本などで楽しく遊べます。
- 保育室開放時間はカレンダーでご確認ください。
カレンダーが表示されない場合はこちらからご覧ください。